この記事でわかること3点まとめ
- 給与や業務量などの負担から社会福祉士はやめとけと言われることがある
- 人の話を親身になって聞けたり、社会課題に関心があったりする人は社会福祉士に向いている
- 社会福祉士になるには、厚生労働省が定める受験資格を満たし、国家試験に合格する必要がある
「社会福祉士はやめとけ」と言われることもありますが、それは本当なのでしょうか?
たしかに、社会福祉士には大変な面や厳しい現実もあります。しかしその一方で、人の人生を支えるという大きなやりがいや、専門性を活かして社会に貢献できる魅力も兼ね備えた職業です。
本記事では、「やめとけ」と言われる背景やその理由をはじめ、社会福祉士として働くメリット、向いている人・向いていない人の特徴など、社会福祉士を目指す前に知っておきたい情報をわかりやすく解説します。
社会福祉士の仕事に興味がある方や、福祉系の進路を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。
>>>東京の社会福祉士専門学校をご覧になりたい方はこちら
>>>名古屋の社会福祉士専門学校をご覧になりたい方はこちら
社会福祉士はやめとけと言われる理由
社会福祉士が「やめとけ」と言われる理由には、主に3つの現実的な側面があります。
- 給与水準が高くない
- 業務量が多く責任が重い
- 感情的な負担が大きい
それぞれ詳しく解説します。
給与水準が高くない
社会福祉士が敬遠される理由の一つに、給与水準の低さがあります。厚生労働省の職業情報提供サイト(job tag)によると、社会福祉士を含む福祉ソーシャルワーカーの平均年収は約441万円です。
一方、国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」では、日本人の平均年収は約460万円円。これと比較すると、社会福祉士の年収は全国平均よりも約19万円低い水準です。
ただし、この年収データには、資格を持たない職員や非正規雇用のスタッフも含まれており、正社員の社会福祉士に限定すれば、実際には全国平均と同程度、またはそれ以上になるケースもあります。特に、50~54歳の年収は平均485万円となっており、経験を積めば着実に収入が上がる職種でもあります。
とはいえ、慢性的な人手不足や、処遇改善が進んでいない職場も一部存在するため、「仕事量のわりに給料が見合わない」と感じる人がいるのも事実です。
参照:福祉ソーシャルワーカー|職業情報提供サイトjob tag|厚生労働
業務量が多く責任が重い
社会福祉士は、利用者の相談援助を中心に、行政や医療機関との連携、各種手続きの支援、報告書や計画書の作成など、多岐にわたる業務を担います。
特に、担当件数が多い施設や地域では、時間に追われる日々が続くことも珍しくありません。さらに、支援が必要な人々に寄り添う仕事だからこそ、判断や行動に対して大きな責任が伴います。
その結果、精神的なストレスやプレッシャーを感じやすく、「自分には向いていない」と感じて離職するケースもあります。業務の複雑さと責任の重さが、「やめとけ」と言われる背景の一つです。
感情的な負担が大きい
社会福祉士が直面するのは、生活困窮、虐待、DV、孤独死、精神疾患など、深刻な課題を抱えた人々です。こうした現場では、感情的なつらさや葛藤が避けられないことも多くあります。
利用者や家族の苦しみに寄り添うことで、やりがいを感じる反面、自分自身がメンタル的に疲弊してしまうこともあります。とくに、感情移入しやすいタイプの人や、気持ちの切り替えが苦手な人にとっては、感情的な負担が大きくなりやすい仕事です。
社会福祉士の仕事内容

社会福祉士は、生活に困難を抱える人々を支援する専門職です。その仕事内容は多岐にわたり、単なる相談業務にとどまらず、制度の活用支援や関係機関との連携、記録・書類作成まで多様な業務を担います。
ここでは、社会福祉士の代表的な仕事内容を紹介します。
相談支援と生活課題の解決
社会福祉士の主な役割は、社会生活の中で問題を抱える人の相談に応じ、解決に向けた支援をおこなうことです。対象となるのは、以下のような人々です。
- 児童
- 障がい者
- 高齢者
- 生活困窮者
対象者のニーズに応じて、医療・福祉・介護・教育・行政などの分野を横断して、制度の紹介や利用支援、生活全体のサポートをおこないます。問題の根本にアプローチし、本人や家族の生活の質を高めることが、社会福祉士の使命です。
関係機関との連携・コーディネート
社会福祉士は、支援対象者が適切な支援を受けられるよう、関係機関と連携・調整をおこないます。医療機関、行政機関、介護サービス、NPO、地域住民など、多くの関係者と情報共有や協議を行いながら、生活課題に対する多面的なアプローチを組み立てます。
例えば、生活困窮者を支援する場合には、就労支援、住居確保、福祉サービスの利用、心のケアなどを組み合わせた包括的な支援が必要です。その際、各機関と連携しながら、調整役として支援全体をまとめる「コーディネーター」としての役割が重要になります。
書類作成や記録業務
相談支援の裏側では、記録や書類作成といった事務業務も欠かせません。具体的には、以下のような書類を作成・管理します。
- 相談記録
- 支援計画書
- 経過報告書
- 関係機関への提出資料
これらは、支援の継続性を保ち、他のスタッフとの連携をスムーズにするために重要な業務です。また、支援の成果や課題を客観的に示すうえでも、正確な記録が求められます。職場によっては事務作業の割合が大きいこともあり、PCスキルや文章力も社会福祉士には必要とされます。
社会福祉士の資格を取得するメリット
社会福祉士の資格を取得することで、専門職としての信頼性が高まり、働く場や将来のキャリアの幅も広がります。ここでは、社会福祉士資格の主なメリットを3つ紹介します。
国家資格として専門性を証明できる
社会福祉士は「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく国家資格であり、福祉分野における専門性を公的に証明できる資格です。相談援助に関する高度な知識と技術を持つことの証明となるため、就職・転職時のアピールポイントにもなります。
また、福祉の現場では資格の有無が採用条件になるケースも多く、社会福祉士を取得していることで選択肢が大きく広がります。
働ける環境が広がる
社会福祉士の資格を持っていると、福祉施設だけでなく、病院や行政機関、教育機関など、活躍の場が多岐にわたります。具体的な勤務先には以下のようなものがあります。
- 特別養護老人ホームなどの介護施設
- 障がい者支援施設
- 児童相談所・児童福祉施設
- 地域包括支援センター
- 学校(スクールソーシャルワーカー)
- 市区町村の福祉職(公務員)
このように、福祉の現場に限らず、地域や社会全体を支える職場で活躍できるのが魅力です。安定した雇用や公的機関での勤務を希望する方にも適した資格です。多方面で活躍できます。
キャリアアップ・昇進に役立つ
社会福祉士はキャリアアップの際にも強みとなります。現場経験を積みながら、主任相談員や管理職(例:施設長・介護部長)などの役職に就くケースも多く、昇進や処遇改善にもつながります。
また、将来的には独立開業して、成年後見人として活動したり、福祉関連の研修講師やコンサルタント、専門相談員として働くことも可能です。
さらに、ステップアップとして「認定社会福祉士」「認定上級社会福祉士」などの上位資格を取得すれば、より専門的かつ高度な業務に携わる道も開けます。キャリア形成においても有利な資格といえるでしょう。
社会福祉士に向いている人の特徴

社会福祉士は、多様な支援を必要とする人と関わる専門職です。ここでは、社会福祉士としての資質がある人に共通する特徴を紹介します。
人の話を親身になって聞ける
相談援助を担う社会福祉士にとって、相手の話をじっくりと聴く姿勢は何よりも重要です。悩みや苦しみを抱える方に対し、しっかりと耳を傾け、気持ちに寄り添うことが求められます。
共感力があり、相手の立場に立って考えられる方は、信頼関係を築きやすく、適切な支援につなげやすいため、社会福祉士として非常に適性が高いといえるでしょう。
社会課題への関心がある
社会福祉士は、貧困、虐待、高齢化、障がい、孤立といった社会課題の最前線で支援をおこないます。こうした問題に対して強い関心を持ち、「社会を少しでも良くしたい」「困っている人の力になりたい」という思いを持っている方は、仕事にやりがいを感じながら取り組むことができるでしょう。
社会の変化に敏感であり、現場で求められる支援を自ら考え、行動に移せる方は、社会福祉士としての適性が高いといえます。
困難な状況でも前向きに行動できる
社会福祉士の現場では、思うように物事が進まないケースや、支援が長期化する場面も少なくありません。ときには葛藤や無力感を抱えることもあるでしょう。
そんななかでも、あきらめずに地道な努力を続けられる粘り強さや、前向きな姿勢を保てる方は、困難な状況でも利用者や関係機関からの信頼を得やすく、長く現場で活躍できます。
首都医校/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。
気になる方は下記のリンクをクリック!
>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る
また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。
社会福祉士に向いていない人の特徴
社会福祉士の仕事には、精神的なタフさや柔軟な対応力が求められます。以下のようなタイプの人は、社会福祉士に向いていない可能性があるため、事前に自分の適性を確認しておくことが大切です。
感情を引きずりやすい
社会福祉士は、虐待や貧困、障がい、孤立など深刻な悩みに直面する人と関わる仕事です。感受性が豊かなことは長所でもありますが、利用者のつらい気持ちに過度に共感しすぎると、自身が精神的に疲弊してしまう恐れもあります。
そのため、利用者とは適切な距離感を保ち、必要に応じて感情をコントロールする力が求められます。感情を引きずりやすい人は、日々の業務でストレスを抱え込みやすいため注意が必要です。
曖昧な状況にストレスを感じやすい
社会福祉士の支援は、すぐに成果が出るとは限りません。利用者によって状況や問題の背景が異なるため、マニュアルどおりに対応できないケースも多くあります。
支援の方向性が見えにくかったり、結果が出るまでに時間がかかったりすることに対してストレスを感じやすい人は、業務に対する不安や焦りを感じやすい傾向にあります。そうした状況でも、前向きに対応を続けられるかが問われます。
調整や交渉が苦手
社会福祉士の仕事では、本人だけでなく家族や関係機関、行政、医療機関などとの連携が欠かせません。利用者を取り巻く多様な立場の方と意見をすり合わせながら、支援の方針を決める必要があります。
そのため、調整や交渉が苦手な方、あるいは人とのやり取りにストレスを感じやすい方は、業務を円滑に進めにくいと感じることがあるでしょう。対人関係に不安がある場合は、社会福祉士という仕事が自分に合っているか慎重に検討することをおすすめします。
社会福祉士として働くには
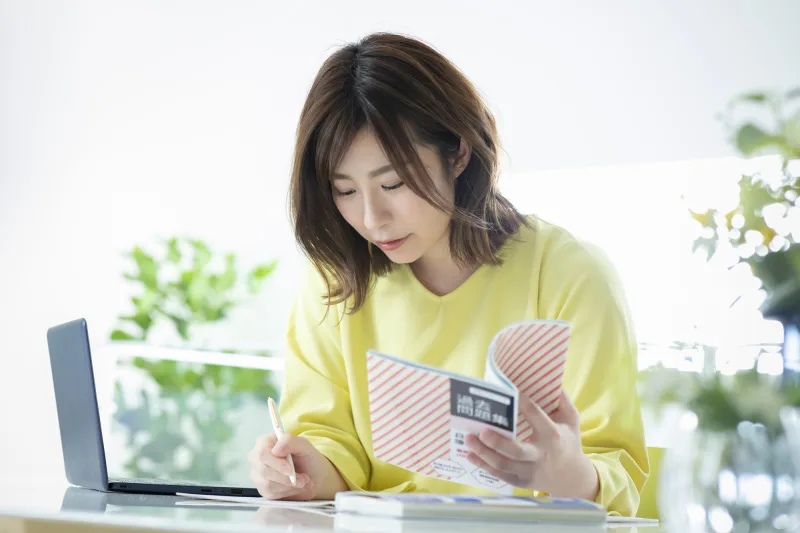
社会福祉士として働くには、厚生労働省が定める受験資格を満たし、国家試験に合格する必要があります。社会福祉士は国家資格であり、一定の専門知識と実務能力が求められる職業です。
国家試験の受験資格は、以下のいずれかのルートで取得するのが一般的です。
- 福祉系の4年制大学で指定科目を履修する
- 福祉系の短期大学や専門学校で基礎科目を修了した後、短期養成施設で6ヵ月以上学ぶ
- 一般大学や一般短期大学を卒業後、指定の養成施設で1年以上学ぶ(※一般短期大学卒業者は実務経験が必要)
これらのルートを経て受験資格を得たうえで、毎年1月ごろに実施される国家試験に合格すれば、晴れて社会福祉士として登録・就業が可能となります。
なかでも専門学校は、現場で求められる実践力を効率的に習得できるカリキュラムが整っており、卒業後の就職にもつながりやすいのが特徴です。短期間で国家試験合格を目指したい方や、現場経験を重視したい方には、専門学校の進学が効果的な選択肢となるでしょう。
首都医校/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。
気になる方は下記のリンクをクリック!
>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る
また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。
専門学校について、下記記事でも詳しく解説しています。
>東京の社会福祉士専門学校はおすすめ?社会人でも通える?学費や支援制度などを解説
>社会福祉士を目指せる学校の種類|専門学校に通うメリットを解説
まとめ
社会福祉士は、一部で「やめとけ」と言われることもありますが、それは給与面や業務の大変さといった一側面に過ぎません。実際には、資格を取得することで専門性が証明され、就職・転職に有利となるほか、働ける分野も多岐にわたるため、将来的なキャリアアップも十分に見込める魅力的な職業です。
人と関わることが好きな方や、社会的な課題に興味がある方であれば、大きなやりがいを感じながら働くことができるでしょう。
社会福祉士を目指す際は、基礎知識と実践力をバランスよく身につけられる専門学校での学びが近道になります。実践的なスキルを備えた人材は、現場でも高く評価されやすく、活躍のチャンスが広がります。
人々の生活を支える専門職として、社会福祉士を目指してみませんか? あなたの一歩が、誰かの人生を変える力になります。
首都医校・名古屋医専の社会福祉士学科で学びませんか?
首都医校では、実践に強い社会福祉士として活躍できるよう1年間で集中的に学べるカリキュラムを整えています。高齢者、障がい者などの関連施設や病院で年間260時間の実習を実施するため、現場で活かせる実践力が身につきます。
さらに、経験豊富な専門家による「国家試験対策」と「就職指導」が充実している点も特徴です。試験対策では全国模試を活用して課題を洗い出すことで弱点を克服し、合格率は96.1%と高い水準を誇ります(※2024年・2025年3月平均実績)
社会福祉士学科で、社会福祉士を一緒に目指しましょう。

社会福祉士学科
1年間で学ぶ社会福祉士学科では、前期に相談援助の知識や技術、ソーシャルワーカーとしての価値・理論を学びます。後期には現場での総仕上げとなる実習に取り組みながら、全国模試を活用した国家試験対策で合格を目指します。
首都医校/名古屋医専では、イベント/オープンキャンパスを随時開催中。
気になる方は下記のリンクをクリック!
>名古屋(名古屋医専)のイベント/オープンキャンパス情報を見る
また、「学校案内パンフレット」「学費、住まいのサポートBOOK」「保護者向け冊子」「入学要項」「エントリー/出願書類一式」が資料を無料で送付しています。気になる方は下記をご覧くださいませ。
