言語聴覚士はリハビリテーション職の1つで、主に「話す、聞く、食べる」ことに関する支援をおこないます。
今回は言語聴覚士を目指す方に向けて、なり方や仕事内容、向いている人、国家資格など幅広くご紹介します。
この記事でおすすめする言語聴覚士専門学校は下記リンクからご覧いただけます。
言語聴覚士とは?
言語聴覚士は、「話す、聞く、食べる」ことのスペシャリストで、言葉によるコミュニケーションに問題を抱える方の支援をおこないます。
ST(Speech-Language-Hearing Therapist)とも呼ばれます。
言語聴覚士の仕事内容
言語聴覚士は、ことばによるコミュニケーションや食べることに問題を抱える方に対し、訓練や指導などをおこない支援します。
ことばによるコミュニケーションには、言語・聴覚・発声・発音・認知などさまざまな機能が関係しています。これらの機能は、事故や病気、加齢、発達の問題などによって障害が生じることがあります。
なぜことばや食事に問題が起きているのかを明確にし、適切なアプローチをおこなうのが言語聴覚士の仕事です。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
- 脳卒中で失語症になった患者さんに、発語器官・呼吸筋の訓練をおこなう
- 耳が聞こえにくい子どもに、聞き取りや発音の訓練をおこなう
- 食べ物でむせやすくなった高齢者に、嚥下訓練をおこなう
言語聴覚士が活躍できる分野
言語聴覚士は、幅広い分野で活躍できます。
- 医療
病院や診療所などの医療分野で働く言語聴覚士は多く、実際、日本言語聴覚士協会会員の6割は医療機関に所属しています。
主に、病気やケガによる言語障害に対してリハビリをおこないます。
- 介護
介護保険施設などで、高齢者のサポートをおこなう言語聴覚士もいます。
加齢・認知症などが原因で発声や耳の聞こえに問題を抱え、コミュニケーションが難しくなった高齢者や、嚥下障害を抱える高齢者に対してリハビリをおこないます。
- 福祉
障がい者福祉施設、児童福祉施設、保健所などの福祉分野でも、言語聴覚士は活躍しています。
話す、聞く、食べることに問題を抱える障がい者や子どもに対し、リハビリを実施します。
言語聴覚士のやりがい
言語聴覚士のやりがいは、やはりリハビリテーションの成果が出たときです。
言語聴覚士が取り扱う「話す、聞く、食べる」という動作は日常のなかでも重要であり、失われることで生活の質も大きく下がってしまいます。
リハビリによってそうした機能を改善することで、患者さんの生活を健康に、より豊かにできます。
「以前と同じように話せるようになった」「安心して食事を楽しめるようになった」という患者さんの喜びの声を聞くことで、言語聴覚士は大きなやりがいを感じることができるでしょう。
言語聴覚士になるためには

言語聴覚士になるには、養成校に通ったあと、国家試験に合格する必要があります。
言語聴覚士養成所に入学する
文部科学大臣や各都道府県知事が指定する、言語聴覚士養成所に入学します。
次のように、最終学歴によって進路が異なります。
- 高卒者:大学・短大・専修学校(3〜4年制)
- 一般大卒者:大学または大学院の専攻科・専修学校(2年制)
国家試験の受験資格を得る
上記の言語聴覚士所で教育課程を修了することで、言語聴覚士国家試験の受験資格が得られます。
養成所では、次のようなことを学ぶのが一般的です。
- 基礎・専門基礎科目:医学、心理学、言語学など
- 専門科目:言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、発声発語・嚥下障害学など
- 臨床実習:病院やリハビリセンターなどでの実習
言語聴覚士の国家資格を取得する
言語聴覚士の国家資格取得のため、試験を受けます。
試験は毎年2月に実施され、筆記形式です。
合格率は50%〜60%と一見難しいようですが、既卒者を含めた合格率のため低くなっています。
養成所の新卒者の合格率は80%程度のため、養成所でしっかり試験対策をすることが重要であることがわかります。
言語聴覚士として働く
国家試験に合格し、資格を取得すると言語聴覚士として働くことができます。
養成所によっては就職サポートをおこなっている場合もあるため、学校をえらぶときは、どんな就職サポートが受けられるかを1つのポイントにして探すのもよいでしょう。
言語聴覚士を目指せる学校の種類
言語聴覚士を目指せるのは、文部科学大臣や各都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所です。
具体的には、次のものが挙げられます。
専門(専修)学校
専修学校のうち、専門課程を設置しているものを専門学校と呼びます。
実習や就職サポートに力を入れている学校も多いのが特徴です。
国家試験の受験資格を得るためには、高校卒業後すぐに入学する場合3〜4年制、一般大学を卒業している場合は2年制の学校に通います。
大学
大学では、4年間で一般教養も含めて幅広く学びます。
大卒者の場合は、専攻科で2年間学べば言語聴覚士試験の受験資格が得られます。
短期大学
高卒者の場合、短期大学で勉強するという選択肢もあります。
大学よりも短い期間で効率よく学びたい方におすすめです。
言語聴覚士に向いている人
ここでは、言語聴覚士に向いている人の特徴をご紹介します。
根気強い人
リハビリテーションは、長い期間をかけておこないます。
患者さんが諦めずにリハビリを続けるには、言語聴覚士が根気強くサポートし続けることが大切です。
そのため、根気強く何かに取り組んだ経験のある人は、言語聴覚士に向いているといえます。
洞察力がある人
ことばによるコミュニケーションが難しい患者さんを相手にすることが多い言語聴覚士にとって、洞察力は必須のスキルです。
どのようなリハビリテーションが必要なのか、患者さんの様子を見ながら決定します。また、リハビリ中に患者さんの表情や仕草から回復の程度を見たり、場合によってはプランを変更したりする場合もあります。
人と関わることが好きな人
言語聴覚士をはじめとするリハビリテーション職にとって、「人と関わることが好き」という気持ちはとても重要です。
言語聴覚士には、患者さんに寄り添い、信頼関係を築くことが求められます。
患者さんの求めていることを察知し、ときに励まし、共感することで、リハビリテーションをやり遂げられるようサポートします。
言語聴覚士に求められるスキル
言語聴覚士には、以下のようなスキルが求められます。
言語聴覚士として成長するためには、これらのスキルを意識的に磨き続けることが重要です。患者一人ひとりのニーズに合わせた適切なサポートを提供できるよう、常に自己研鑽に励むことが求められます。
正しい知識と技術
患者さんに適した支援を提供するため、正しい専門知識と技術が必要です。
人間の発声や聴覚、嚥下に関わる構造や機能への理解をはじめ、失語症、構音障害、聴覚障害、摂食・嚥下障害など、さまざまな疾患や障害の原因と治療法への知見が求められます。
柔軟な考え方や問題解決能力
患者さんの状況に応じた柔軟な対応や問題解決能力が求められます。
患者さんの年齢や障害の度合い、生活環境に合わせた訓練プログラムを作成するスキル。訓練の進捗や患者の状態に応じて、計画を調整する柔軟性。訓練をより効果的かつ楽しいものにするため、さまざまな問題を解決していく必要があります。
心理的なサポート力
多くの患者さんは、障害に対して不安やストレスを感じており、心理的ケアも言語聴覚士の重要な役割です。
患者さんやご家族の感情に寄り添い、安心感を与えることはも大切です。訓練を続けるために、患者さんのやる気を引き出すサポートをおこない、精神的な負担を軽減し、リハビリに集中できる環境を作る力が求められます。
観察力と分析力
患者さんの小さな変化を起こした瞬間、効果的な支援をおこなうための観察力と分析力が必要です。
患者の言語や発声、聴覚、嚥下の状態の変化を正確に観察することをはじめ、訓練の成果や問題点を数値やから分析し、次のステップを計画することが求められます。
学習意欲と向上心
医療やリハビリテーションの分野は日々進化しているため、最新の知識や技術を学び続ける姿勢が求められます。
学会や研修への参加をはじめ、医師や看護師、理学療法士など、他の医療従事者からの知識を吸収して、自分のスキルや知識を高める必要があります。
言語聴覚士の将来性
言語聴覚士の需要は今後さらに高まると予想され、将来性は非常に高いと言えます。以下理由から将来性が高いと言えます。
高齢化社会によるニーズの拡大
日本の少子高齢化は進んでおり、言語聴覚士の活躍が必要な場面が増えています。
嚥下障害患者の高齢者への摂食・嚥下リハビリの支援、認知症患者への言語訓練やご家族への指導、病院だけでなく、介護施設や訪問リハビリでの仕事も増えており、活躍の場が広がっています。
教育・研究分野での要望
言語聴覚士の専門性を社会に広めるための教育・研究分野のニーズもあります。
専門学校や大学で人材を育成するための教育者としての活躍をはじめ、嚥下や言語に関する新たな知見を追求し、研究分野での貢献が求められています。
キャリアパスの多様化
言語聴覚士は、その専門性を活かしてさまざまなキャリアパスを選ぶことができます。
訪問リハビリや地域医療、リハビリ機器メーカーでのリハビリ指導や商品開発、自営業やフリーランスなど、病院だけでなく、さまざまな環境で活躍できます。
言語聴覚士に関する資格
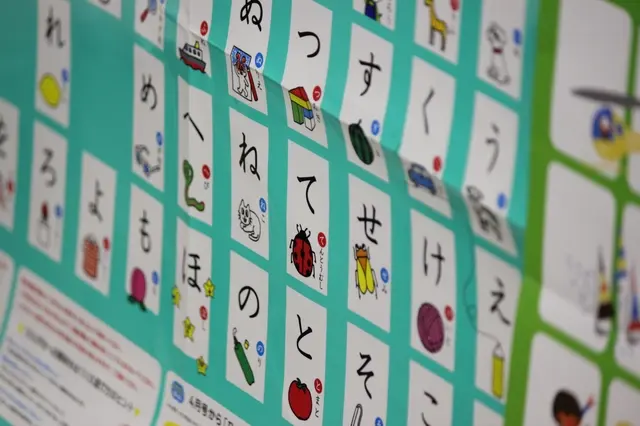
言語聴覚士国家資格
言語聴覚士になるには、国家試験に合格し、資格を得る必要があります。
言語聴覚士の国家試験は、マークシートの筆記形式です。
以下のように試験科目が非常に多く、幅広い知識が求められます。
| 基礎医学、臨床医学、臨床歯科医学、音声・言語・聴覚医学、心理学、音声・言語学、社会福祉・教育、言語聴覚障害学総論、失語・高次脳機能障害学、言語発達障害学、発声発語・嚥下障害学及び聴覚障害学 |
「言語聴覚士国家試験の施行|厚生労働省」より引用
合格のためには、時間をかけて試験対策することが大切です。そのため、多くの言語聴覚士養成所では、国家試験対策をおこなっています。
言語聴覚士を目指すなら首都医校・大阪/名古屋医専がおすすめ
首都医校・大阪/名古屋医専は医療・福祉からスポーツ系分野までを網羅し、チーム医療に対応するエキスパートを育成する専門学校であり、「国家資格 合格保証制度」「完全就職保障制度」2つの保証制度があることで、希望者就職率は100%を実現しております。首都医校(言語聴覚士 専門学校(東京))大阪医専(言語聴覚士 専門学校(大阪))名古屋医専(言語聴覚士 専門学校(名古屋))で言語聴覚士を一緒に目指しましょう。
まとめ
言語聴覚士は、「話す、聞く、食べる」ことのスペシャリストとして、リハビリテーションなどによって言語や聴覚、食事に問題を抱える方を支援します。
「人の役に立ちたい」「感謝される仕事がしたい」と考えている方にぴったりの仕事といえます。
言語聴覚士になるには、特定の養成所に通い、国家試験に合格する必要があります。
まずは、言語聴覚士を目指せる学校を探すところからスタートしてみましょう。
